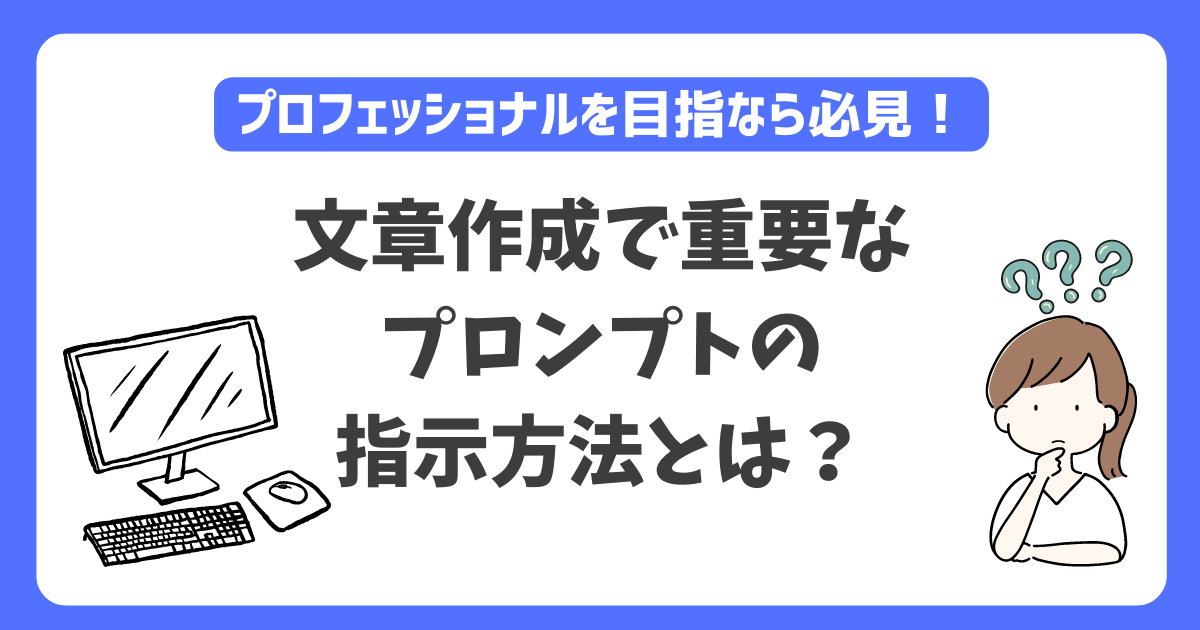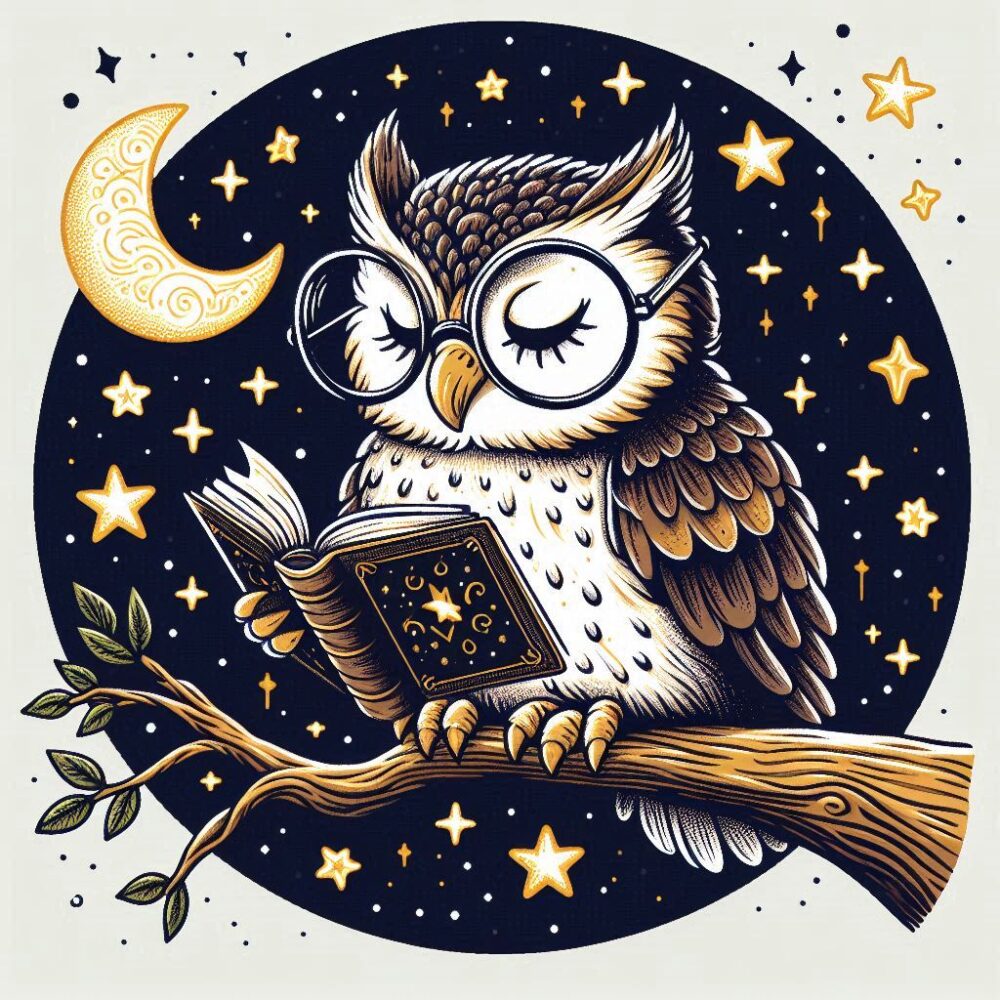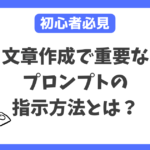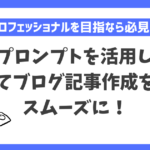前回は初心者の方でも分かりやすい文章作成のプロンプト指示方法について、説明しましたが次は少し深掘りしたプロンプトの作成方法を元講師の私が詳しく解説します。この記事では、わかりやすく、具体的な指示方法やGPTとの関連性、カテゴリとタブ(要素)の揃え方などを解説しています。この記事を読めば、さらにプロンプト作成で効率的な文章作成ができるようになることでしょう。
プロンプトエンジニアガイドは読む価値あり!
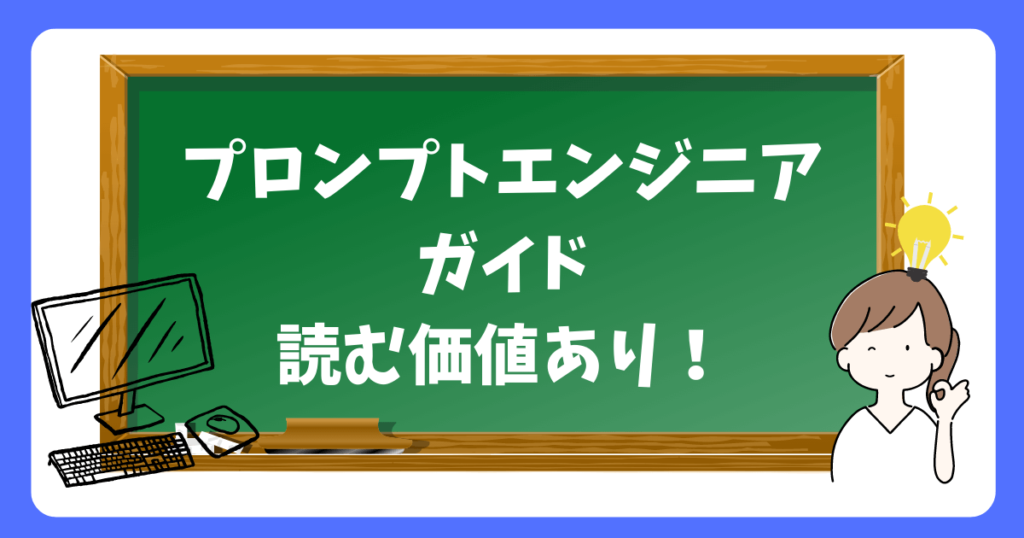
プロンプトエンジニアリングガイド日本語版2023年4月対応!
元々英語版であったプロンプトの論文が日本語版で読みやすくなっていますので参考にしてください。今回の記事はプロンプトエンジニアリングガイドより、「ゼロショットプロンプティング」から「フォーショットプロンプティング」「チェインオブソートプロンプティング(CoT)」などを最初に紹介します。興味がある方は原文を見てね。
- 「ゼロショットプロンプティング」
いきなり指示 - 「フォーショットプロンプティング」
例文を与えて指示 - 「チェインオブソートプロンプティング」(CoT)
中間的な推論ステップを経て指示する - 「ゼロショットCoTプロンプティング」
“ステップバイステップで考えてみましょう“を追記する - 「連鎖思考プロンプティング」(自己整合成)
「フォーショット(例文)」と「CoT(推論ステップ)」を掛け合わせた指示 - 「知識生成プロンプティング」
プロンプトで事前に知識やルールを生成させ指示を出す - 「自動プロンプトエンジニア」(APE)
AIに“自動指示生成“と“選択“を生成させるフレームワーク - 「方向性刺激プロンプト」
ヒントを与える
以上8つ以外にも検証中の方法なども更新されていくようなのでプロンプト作成に立ち止まってしまったら読み返してみると良いアイディアが湧いてくるかもしれませんね。
これがすごい!「自動プロンプトエンジニア」(APE)
Automatic Prompt Engineer (APE)オートマティック プロンプト エンジニア(通称:エイピーイー)
これは,最初にタスク(目的達成)のための指示候補から、候補解を生成。検索手順を指導してくれます。候補解はターゲットモデルを使用・内部の評価スコアに基づいて最適な指示が選択される。
このプロンプトを用いて「APEはゼロショットCoTプロンプト(一緒にステップバイステップで考えてみましょう)」を発見した。
・Auto Prompt:購買誘導型
・Prefix Tuning:NLGタスクのためのトレース可能な連続プレフレックスを前置する、ファインチューニングの軽量な代替え案
・PrimptTuning:逆伝播を通じてソフトプロンプトを学習するメカニズムを提案
私は英語版を翻訳させて読みましたがニュアンスの違いで結構理解が変わってしまいました。日本語版で表示されない時は左下の「English」を「日本語に」変えると翻訳されます。ので一見の価値はあります。
では今回の検証に移ります
プロンプトを効果的に使うために必要な冒頭ワードとは?
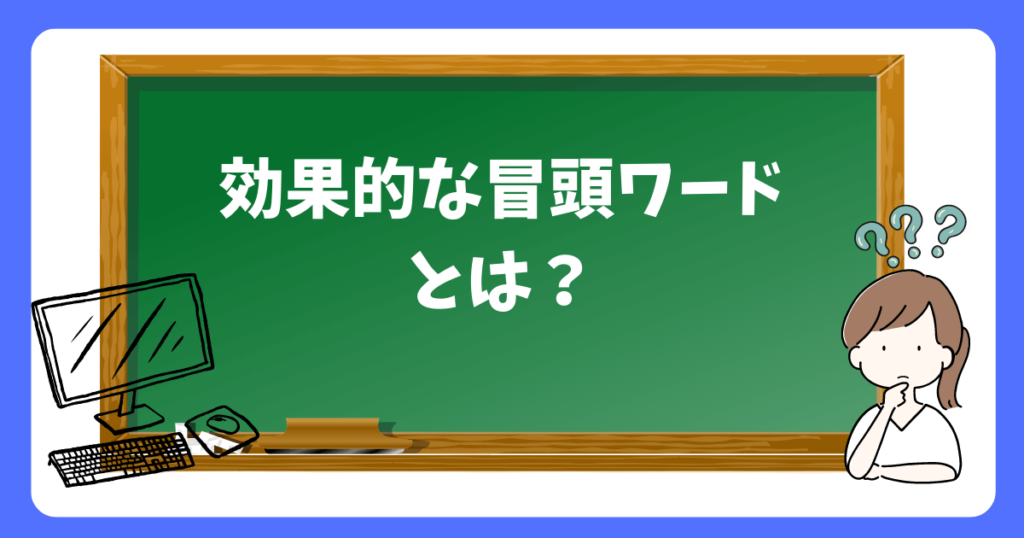
「宣言」「テーマ」「目的」この様なカテゴリを入れることが多いが、文章の内容にもよるが、「目的」が一般的でAIが理解しやすい。
言葉のニュアンスが違うだけで得られる結果も異なることもありますし,出力したい内容によっても使うカテゴリが変わります。ここでは一般的にはと言う前提で「目的」の文章を記述するのがAIには理解しやすいです。
目的を明確にするためにプロンプトの指示に従う
事前準備として考察する内容は次の通りです。
- 目的を明確にする:分析したい内容や調べたいことを明確にします。
- キーワードを選ぶ:目的に合わせて、分析や調査に必要なキーワードを選びます。
- プロンプトを書く:選んだキーワードを使って、プロンプトを書きます。プロンプトには、調査のために必要な情報や、答えを得たい質問などを含めます。
- プロンプトの精度を上げる:より高い精度で分析を行うために、条件、制約、手順、注意点など、より具体的な情報をプロンプトに追加することができます。
以上の手順を参考にして、プロンプトを作成することができます。プロンプトは、分析や調査のための基本的な質問をまとめたものであるため、しっかりと作成することが重要です。
【プロンプト作成のテンプレート】
- 目的を明確にする
- 解決したい課題を特定する
- 必要な情報を洗い出す
- 適切なキーワードを選定する
- キーワードを組み合わせて文章を構成する
- プロンプトを修正・改善する
深掘りしていくためのプロンプトの順番とは?
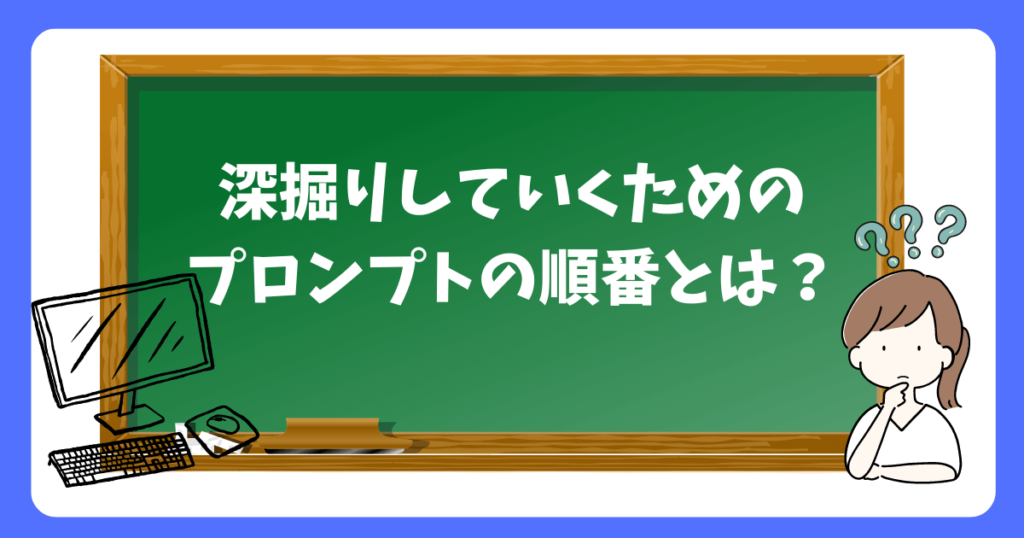
1回のプロンプトで自分の知りたいことを抽出するため(今回の目的)のプロンプトを書き直しを行いながら進んでいきたいと思います。(プロンプトと出力結果を載せていきますのでここから長文です。)
事前情報
- 目的を明確にする 今回の題材として「Chat GPTと学校教育に影響を明確にする」を目的にしていきたいと思います
- 解決したい課題を特定する 課題は「Chat GPTは学校教育に影響が出るかどうか?」
本題
ここからChat GPTを使っていきましょう。
必要な情報を洗い出す では、情報をChat GPTに「ゼロショットプロンプト」でそのまま聞いてみましょう。

「Chat GPTと学校教育の影響について明確にしてください。」
「Chat GPTは、自然言語処理を用いて人間のように対話を行うことができる人工知能システムです。一方、学校教育は、学習者に対して知識や技能を教授するための教育プロセスです。これら2つの概念には直接的な関係はありませんが、技術革新によって教育の方法やアプローチが変化する可能性があります。 Chat GPTのような人工知能技術は、教育においても様々な用途が考えられます。例えば、教育現場において、学習者との自然な対話を可能にするために使用されることが考えられます。また、学習者に対して個別化された学習プランを提供するためにも使用されるかもしれません。ただし、これらの技術を適切に活用するためには、教育者や教育研究者が最新の技術やその効果的な活用方法について常に学習を続ける必要があるでしょう。 一方、学校教育は、現代社会において非常に重要な役割を果たしています。学校教育は、人々に必要な知識や技能を提供するだけでなく、社会化のプロセスにも大きく貢献しています。学校教育は、学習者が自己実現や社会貢献などの目標を達成するための基礎を築くことができます。したがって、学校教育は、社会の発展と人々の成長に不可欠なものと言えます。 まとめると、Chat GPTと学校教育は、直接的な関係はありませんが、技術革新が教育の方法やアプローチを変化させる可能性があります。しかし、学校教育は、現代社会において不可欠なものであり、人々の成長や社会貢献に大きく貢献しています。」
Chat GPTより
長い文章で返してきたのでもう少し短く説明してもらいましょう。 文章を短くして分かりやすくしてみましょう

「Chat GPTと学校教育の影響について明確にしてください。文章は短く要約してください。」
Chat GPTより
「Chat GPTは学校教育に影響を与えることができます。たとえば、自然言語処理技術を用いた教育アプリケーションの開発や、オンライン授業や遠隔教育において、生徒とのコミュニケーションを改善することができます。ただし、Chat GPTは教師や他の教育専門家の代わりになるわけではなく、教育現場においては適切に活用する必要があります。」
もっともらしい答えですが、「①では直接関係性がないと言っていたのに②では影響を与えることができる。」と日本語がおかしい気がしますが、「影響がある」と示しています。この課題については普通に考えても分かれるところなのでなぜ「明確な答えが出ないのか?」もう少し分析を続けて,どの様な分析から答えを出しているのかを探ってみます。
適切なキーワードを選定する どんなことが起因して分析してるのか続けて要素を書き出してもらいましょう。

「次の課題について問題となる要素を書き出してください。Chat GPTと学校教育の影響について明確にしてください。文章は短く要約してください。」
「Chat GPTと学校教育の影響には、以下のような問題があります。
Chat GPTより
- 技術的な問題:Chat GPTはまだ完全ではなく、誤った回答をすることがあります。
- 教育に対する影響:Chat GPTは教育現場に変化をもたらす可能性がありますが、教師や教育専門家の代わりにはなりません。
- 倫理的な問題:Chat GPTが生徒のプライバシーや倫理的な問題に関与することがあるため、慎重に扱わなければなりません。」
今回私が聞きたいのは2番の「教育に対する影響」なのでここを抑えて深掘りしてもらいもらいましょう。

「教育に対する影響:Chat GPTは教育現場に変化をもたらす可能性がありますが、教師や教育専門家の代わりにはなりません。とはもう少し具体的に変化をもたらす可能性の部分を書き出してください。」
「Chat GPTが教育現場にもたらす可能性のある変化には、以下のようなものがあります。
Chat GPTより
学習支援:Chat GPTを用いた教育アプリケーションが開発され、生徒が自分自身で学習を進めることができるようになる可能性があります。質問応答システム:Chat GPTを用いた質問応答システムが教室で使われ、生徒がより深い理解を得ることができるようになる可能性があります。コミュニケーション支援:Chat GPTがオンライン授業や遠隔教育で、生徒と教師とのコミュニケーションを支援することができます。例えば、生徒が疑問に思ったことをChat GPTに尋ね、教師が回答することで、円滑なコミュニケーションが実現する可能性があります。
ポジティブな感じの回答が返ってきましたが、私は学生が悪用した場合などの対策面を知りたいので質問を変えます。

「教育に対する影響:Chat GPTは教育現場に変化をもたらす可能性がありますが、教師や教育専門家の代わりにはなりません。とはもう少し具体的に変化をもたらす可能性の部分を書き出してください。学生が課題などにChat GPTを利用することで教師側が見抜くことが出来ず本人の学習能力を測れなくなる懸念について意見をください。」
「学生が課題などにChat GPTを利用することで、教師側が本人の学習能力を正確に測れなくなる懸念は理解できます。Chat GPTは自動的に回答を生成するため、生徒が理解していなくても正解を出すことができます。このような状況が続くと、教師は生徒の理解度を正確に把握することができず、生徒の学習状況を適切にフォローアップすることができなくなる可能性があります。ただし、教師は生徒の課題提出物や試験など、他の方法を使って生徒の学習能力を測定することができます。Chat GPTを利用する場合でも、教師は生徒が理解しているかどうかを確認するために、補足的な指導を行うことが必要です。」
Chat GPTより
出てきた内容も興味深いものですが、ここではキーワードを拾いたいので、カテゴリや要素を拾っていきましょう。

「上記の文で課題解決に対するカテゴリや要素を箇条書きで表してください。」
上記の文で課題解決に対するカテゴリや要素は以下の通りです。
・学習能力の正確な測定
・生徒の理解度の把握
・適切なフォローアップ
・補足的な指導の必要性
Chat GPTより
出てきた要素をまとめて最初のプロンプトに組み合わせてみましょう。
キーワードを組み合わせて文章を構成する。

「Chat GPTと学校教育の影響について」1つづつ解決してください。文章は短く要約してください。 学校教育の影響・問題
・学習能力の正確な測定
・生徒の理解度の把握
・適切なフォローアップ
・補足的な指導の必要性」
「学校教育におけるChat GPTの影響について、以下のように解決策が考えられます。
学習能力の正確な測定:Chat GPTを利用する場合でも、教師は他の方法を使って生徒の学習能力を測定することができます。例えば、課題提出物や試験などを利用することで、生徒の理解度を正確に測定することができます。
生徒の理解度の把握:教師はChat GPTを利用する場合でも、生徒の理解度を把握するために補足的な指導を行うことが必要です。Chat GPTを使った回答に対して、教師がフィードバックを行うことで、生徒の理解度を確認することができます。
適切なフォローアップ:生徒の理解度が不十分な場合、教師は適切なフォローアップを行うことが必要です。教師は生徒とコミュニケーションをとり、生徒の理解度に応じた指導方法を選択することが重要です。
補足的な指導の必要性:Chat GPTはあくまで補助的なツールであり、教師の代替にはなりません。教師は生徒に対して、Chat GPTを使った回答についての補足的な指導を行うことが必要です。生徒に対して理解しやすいように、例や具体的な説明を加えることで、生徒がより深い理解を得られるようになります。」
Chat GPTより
ちょっと読みづらいのでマークダウン記法で書き直してもらいましょう。プロンプトを修正・改善します

「 「Chat GPTと学校教育の影響について」1つづつ問題を解決してください。文章は短く要約してマークダウン記法を使い問題点を分けて説明してください。
学校教育の影響・問題
・学習能力の正確な測定
・生徒の理解度の把握
・適切なフォローアップ
・補足的な指導の必要性」
「 学習能力の正確な測定 Chat GPTを使うことで、生徒が正解を出すことができても、生徒の学習能力を正確に測定することができなくなる問題があります。教師は、生徒が理解しているかどうかを確認するために、生徒の課題提出物や試験など、他の方法を使って生徒の学習能力を測定する必要があります。
生徒の理解度の把握 Chat GPTを利用することで、生徒が理解していなくても正解を出すことができます。このような状況が続くと、教師は生徒の理解度を正確に把握することができず、生徒の学習状況を適切にフォローアップすることができなくなる可能性があります。教師は、生徒が理解しているかどうかを確認するために、補足的な指導を行う必要があります。
適切なフォローアップ 教師が生徒の理解度を正確に把握できないと、生徒の学習状況を適切にフォローアップすることができなくなる可能性があります。生徒がChat GPTを利用している場合でも、教師は、生徒が理解しているかどうかを確認するために、補足的な指導を行い、適切なフォローアップを行う必要があります
補足的な指導の必要性 Chat GPTを使うことで、生徒が正解を出すことができても、教師が補足的な指導を行わなければ、生徒が理解していないことに気づくことができません。生徒がChat GPTを利用している場合でも、教師は、生徒が理解しているかどうかを確認するために、補足的な指導を行い、適切なフォローアップを行う必要があります。」
Chat GPTより
⑤−1では問題点だけマークダウンで整えられており全体像の説明が抜けています。なのでプロンプトに修正を加えます。

「「Chat GPTと学校教育の影響について」説明し、その後、問題点に対し説明してください。文章は短く要約してマークダウン記法を使い問題点を分けて説明してください。
学校教育の影響・問題
・学習能力の正確な測定
・生徒の理解度の把握
・適切なフォローアップ
・補足的な指導の必要性」
「 Chat GPTと学校教育の影響について Chat GPTは、自然言語処理技術に基づいたAIであり、生徒の学習にも応用される可能性がある。しかし、Chat GPTが教育現場にもたらす影響には問題点も存在する。
学校教育の影響・問題
Chat GPTより
- 学習能力の正確な測定
- 生徒の理解度の把握
- 適切なフォローアップ
- 補足的な指導の必要性」
文章自体ある程度まとまりましたね。 このプロンプトをもとに違うテーマを入れてみましょう。
学校のネタになっているので「夏休みの宿題は必要かどうか」を入れ替えてみます。
内容が混乱すると思いますがそのまま入れます

夏休みの宿題
「「夏休みの宿題は必要かどうか」説明し、その後、問題点に対し説明してください。文章は短く要約してマークダウン記法を使い問題点を分けて説明してください。
学校教育の影響・問題
・学習能力の正確な測定
・生徒の理解度の把握
・適切なフォローアップ補足的な指導の必要性」
「 夏休みの宿題は必要かどうか 夏休みの宿題は、休暇中に生徒が学習習慣を維持するため、また新しい知識を身につけるために与えられる。しかし、夏休みの宿題には問題点も存在する。
学校教育の影響・問題
Chat GPTより
- 夏休みの宿題が過剰になる場合、生徒がストレスを感じる可能性がある。
- 宿題の量や難易度に差がある場合、公平性が失われ、生徒の学習能力の正確な測定が難しくなる可能性がある。
- 宿題の理解度や進捗状況を適切に把握することが難しく、適切なフォローアップができなくなる可能性がある。
- 宿題に取り組む時間や方法によっては、生徒が本来の夏休みの目的であるリフレッシュや休養を十分に取ることができなくなる可能性がある。」
箇条書きの部分が強調されていますが内容はある程度の流れで生成されています。
GPTを使って自動で要素を埋める方法とは?
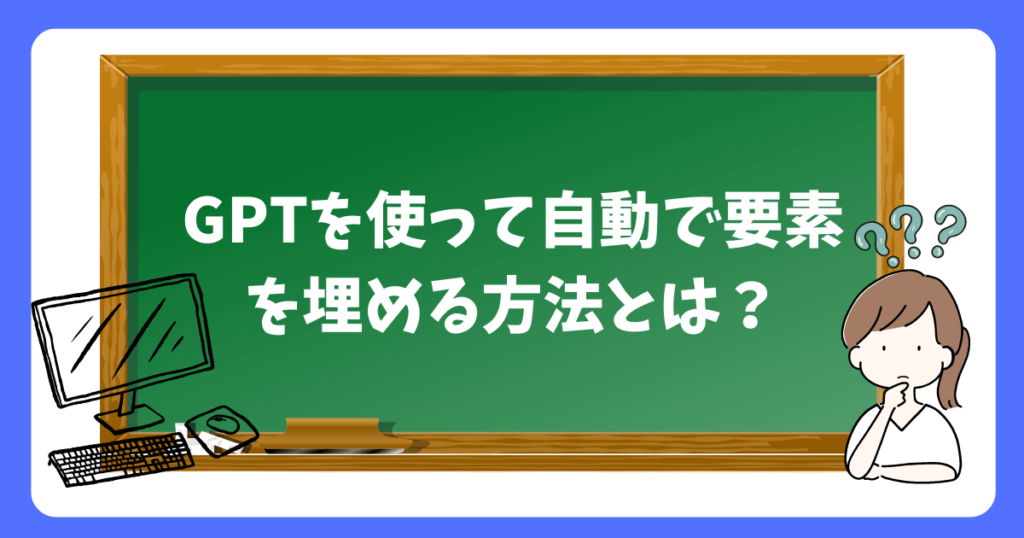
この自然言語モデルの手法APEなどを利用して、空白部分を埋めてもらいます。

夏休みの宿題②
「夏休みの宿題は必要かどうか」説明し、その後、問題点に対し説明してください。文章は短く要約してマークダウン記法を使い問題点を分けて説明してください。
学校教育の影響・問題
・(空白)
・(空白)
・(空白)
・(空白)
夏休みの宿題は必要かどうか
夏休みの宿題については、必要性について賛否両論がある。
学校教育の影響・問題
Chat GPTより
- 宿題によって、学習習慣を定着させることができる。
- 宿題が過剰になり、生徒がストレスを抱える可能性がある。
- 宿題が不十分で、学力向上に寄与しない可能性がある。
- 宿題があっても、放課後の自由な時間を確保できなくなるため、生徒のストレスが高まる可能性がある。」
生成された文集は「夏休みの宿題」ではなく「宿題」について書かれているのかと思われる回答が返ってきている。なぜなら、「夏休みに放課後なんてない」からだ。この様に要素を限定しているようで、理解できていない場合があるので気をつけなければいけない。
それでもある程度プロンプトが形になってきたので、ちょっと応用して「新商品の低迷理由」を聞いてみましょう。

新商品
売り上げ低迷
「「新商品の売り上げ低迷理由」説明し、その後、問題点をあげ、その解決策を説明してください。文章は短く要約してマークダウン記法を使い問題点を分けて説明してください。
売り上げ低迷要因
–
低迷要因に対する解決策
–
新商品の売り上げ低迷理由
新商品の売り上げが低迷している場合、その理由を特定し対策を講じる必要がある。
売り上げ低迷要因
- 製品の魅力的なアピール不足がある可能性がある。
- 価格設定が消費者にとって魅力的ではない可能性がある。
- 販売チャネルやマーケティング戦略が不適切な可能性がある。
低迷要因に対する解決策
Chat GPTより
- 製品のアピールを強化し、魅力を伝えるために、広告やプロモーションを展開することが重要である。
- 価格設定については、競合他社との価格比較や消費者の購買意欲に関する調査を行い、適切な価格帯を設定する必要がある。
- 販売チャネルやマーケティング戦略については、より多くの消費者にリーチできるような販売チャネルやマーケティング戦略を模索する必要がある。たとえば、オンライン販売やSNSマーケティングの活用が挙げられる。」
プロンプト作成ポイント
プロンプト夏休み宿題②を改修して、「文章を要因と解決策」に分けて見出しを追加しています。
文章作成の流れも「説明」「問題点」「解決策」の流れを意識し、ステップバイステップを意識している。そのまま文章に入れると精度が向上する様だがことがテーマ自体が抽象的な内容なので今回は省略している。
このようにプロンプトの指示を具体的にするだけでどんどんブラッシュアップしていくことができるので,筆者はとても面白いおもちゃを与えられた子どもの様に毎日遊んでいる。言葉のニュアンスや文章の前後を変えるだけで変わるため奥が深い。この記事を読むだけでなく実際にいろいろとプロンプトを入力することで体感的に変化がわかるのでチャレンジしてほしい。
【おまけ】プロンプトでよく使われる記号とその意味
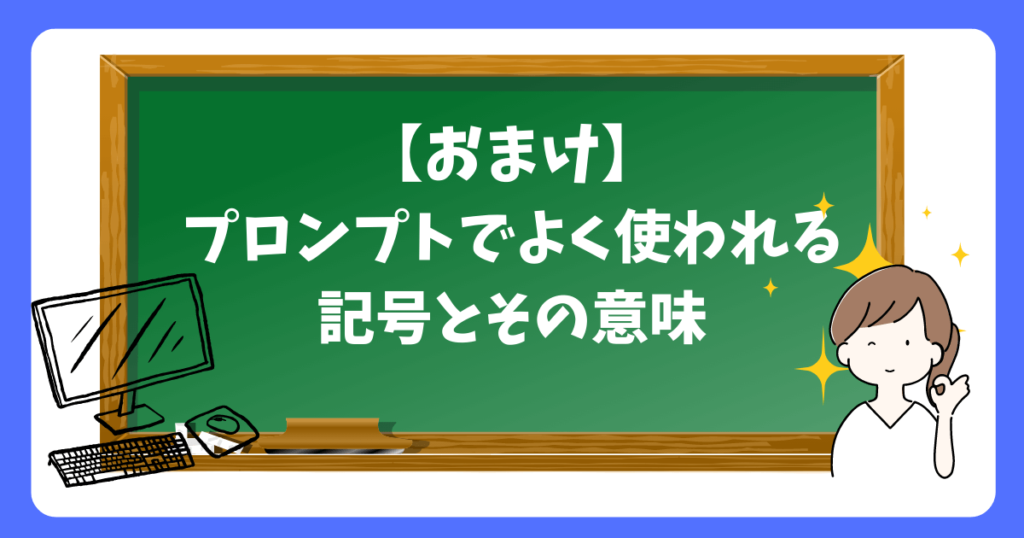
「#」や「“”」「-」など使われているプロンプトをよくみるが何の意味なのでしょう。
AIがプロンプトを理解する上で使われる特殊記号
- カテゴリの指定
プロンプトの冒頭で、どのようなカテゴリの文章を生成したいのかを明確に指定すると、AIが目的を理解しやすくなります。
例:「#レシピ おいしいパスタの作り方を教えてください。」 - 空白を明確にする
複数の単語を含むキーワードの場合、空白を入れて区切ることで、AIが正確に認識しやすくなります。
例:「#旅行 韓国 ソウル 観光スポット おすすめ」 - 記号の使用について
プロンプトに特殊文字を含める場合、ダブルクォーテーション「”」を使用すると認識しやすくなります。また、日本語の句読点や長音符「ー」を使用する場合は、全角のものを使用することが望ましいです。
例:「#小説 “最後に残るのは” 男女の別れの物語」
以上のように、プロンプトを書く際は、できるだけ分かりやすく、正確な表現を心がけることが重要です。
次の文章のAI分析における違いを答えてくだい。
1.#小説 “最後に残るのは” 男女の別れの物語(原文)
2.#小説 最後に残るのは男女の別れの物語(ダブルフォーテーションなし、スペース)
3.#小説 “最後に残るのは” 男女の別れの物語(半角スペース)
4.#小説 :最後に残るのは男女の別れの物語(コロン区切り)
- 小説 最後に残るのは 男女の別れの物語(半角スペース最後・男の前2箇所)
- 「#小説 “最後に残るのは” 男女の別れの物語」は、キーワード「#小説」の後にダブルクォーテーションで囲まれたタイトルが書かれ、その後に空白スペースを挟んで男女の別れの物語というテキストが続いています。
- 「#小説 最後に残るのは男女の別れの物語」は、キーワード「#小説」の後に空白スペースを挟んでタイトルが書かれ、その後にスペースを挟まずに男女の別れの物語というテキストが続いています。
「#小説 “最後に残るのは” 男女の別れの物語」は、キーワード「#小説」の後に空白スペースを挟んでダブルクォーテーションで囲まれたタイトルが書かれ、その後に半角スペースを挟んで男女の別れの物語というテキストが続いています。 - 「#小説 :最後に残るのは男女の別れの物語」は、キーワード「#小説」の後にコロンで区切られたタイトルが書かれ、その後に空白スペースを挟まずに男女の別れの物語というテキストが続いています。
「#小説 最後に残るのは 男女の別れの物語」は、キーワード「#小説」の後に空白スペースを挟んでタイトルが書かれ、その後に半角スペースが最後に1箇所、男の前に2箇所ある形式で、男女の別れの物語というテキストが続いています。
どんな影響があるか?
違いには一般的には以下のような傾向があります。
- (ダブル)クオーテーションマークが入ったキーワードは、その文中で重要な語句であることを示しています。また、クオーテーションマーク自体も一種の特殊記号として扱われ、その中のテキストは一つのまとまりとして解釈されます。
- (ダブル)クオーテーションがない場合でも、スペースで区切られたキーワードは単語単位で解釈されます。
- 半角スペースがある場合は、キーワードが別の単語にくっついているため、精度に若干影響する可能性があります。
- コロンで区切られた場合は、その前のキーワードがタイトルやジャンルを示していることを表している場合があります。
- 最後の例は、スペースが一部省略されているため、文字列としての一体性が失われてしまっています。これによって、キーワード同士の関係性が不明瞭になるため、分析の精度に影響を与える可能性があります。
空白の使い方に注意
自然言語処理において、空白は単語や文章の区切りを表します。空白を含む文書は、トークン化と呼ばれる処理によって単語ごとに分割されます。トークン化は、空白だけでなく句読点や記号も区切りとして認識します。ただし、空白が不適切に使用されている場合、トークン化が正しく行われない可能性があります。例えば、次の文章では、「before」と「after」が別々の単語として認識されます。
“Please arrive before 12:00PM. We cannot accept latecomers after the start of the presentation.”
ここでは、空白の使い方によって、単語の数や文章の意味が変わってしまうことがあるため、適切な空白の使用が重要になります。
AIの分析設定
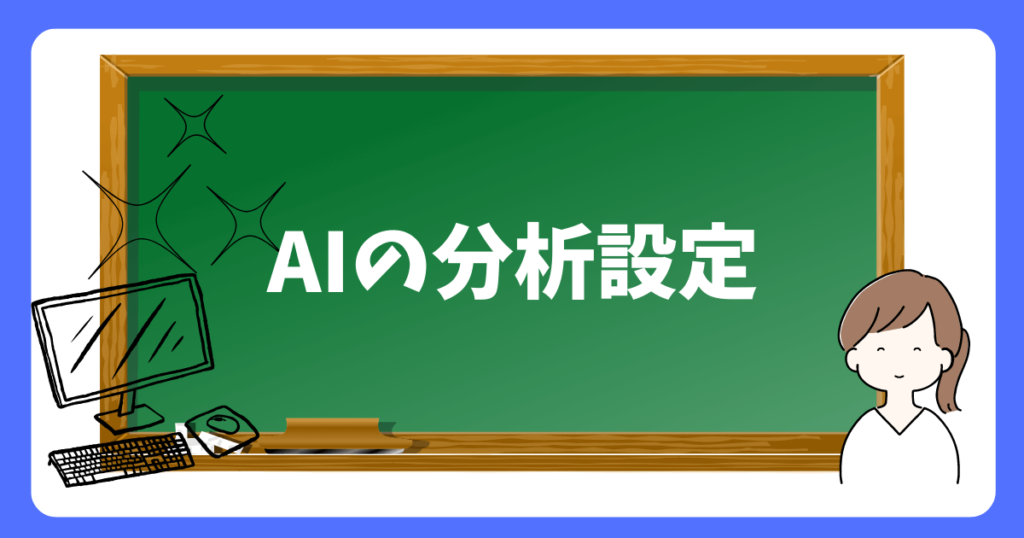
条件の場合
「もし〜なら、〜する」という形式で記述します。具体例としては、「もし明日が雨なら、イベントは中止」というように条件を設定します。
制約の場合
「〜する際には〜しなければならない」という形式で記述します。具体例としては、「商品を購入する際には、会員登録が必要です」というように、必要な制約を明示します。
手順の場合
「まず〜して、次に〜して、最後に〜する」という形式で記述します。具体例としては、「イベント参加申し込みの手順は、まずウェブサイトにアクセスしてフォームに必要事項を入力し、次に申し込み料を支払い、最後に申し込み完了のメールが届くまでお待ちください」というように手順を説明します。
これらの書き方は、プロンプトの文脈に応じて適宜使い分けることが大切です。より正確なプロンプトを作成するためには、その文脈に沿った情報を含めるよう心がけましょう。
目的・目標:
何を達成したいか、何を求めているかを明確にすることで、AIにとってプロンプトの意図が明確になります。
顧客・利用者:
どのような人たちに対して何を提供するのかを示すことで、AIがより正確な情報を提供できるようになります。
比較対象・相関関係:
何を比較したいのか、どのような相関関係があるのかを明確にすることで、AIがより的確な分析結果を出力できます。
期間・時間軸:
どの期間に関する分析なのか、時間軸はどのように設定されているのかを示すことで、AIがより適切なデータを使用して分析を行えるようになります。
ジャンル・カテゴリー:
分析の対象がどのような分野やカテゴリーに属するのかを示すことで、AIがより適切な知識を利用して分析を行えるようになります。
上の例をひとまとまりにテンプレート化
【宣言】
- 〇〇の説明を記述する。
- 〇〇についての質問に答える。
- 〇〇に関するアドバイスを提供する。
【テーマ】
- 〇〇の概要について。
- 〇〇の特徴やメリット・デメリットについて。
- 〇〇の事例や成功例について。
- 〇〇の導入方法や使い方について。
【目的】
- 〇〇の理解を深める。
- 〇〇に関する問題解決を行う。
- 〇〇の導入や活用を促進する。
【条件】
- 〇〇が必要な場合とはどのような状況か。
- 〇〇を実現するために必要な条件や要件は何か。
- 〇〇を実行するための前提条件は何か。
【制約】
- 〇〇を実現するために避けるべき制約は何か。
- 〇〇には遵守しなければならない法的な制約は何か。
- 〇〇の導入や利用には技術的な制約がある場合があるか。
【手順】
- 〇〇を実現するための手順や流れは何か。
- 〇〇を導入するための手順やプロセスは何か。
- 〇〇を実行するための手順や方法を具体的に説明する。
【注意点】
- 〇〇を実行する際に気をつけるべきポイントは何か。
- 〇〇を導入する際に留意すべき点は何か。
- 〇〇を利用する際に必要な注意事項は何か。
ある程度の要素をまとめてみたので、使えるところを選んでプロンプトに組み込んでいただけたらと思います。最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
次回はブログ記事生成のプロンプトを試行錯誤を行いながら私のプロンプト作成手順を書いていきます。